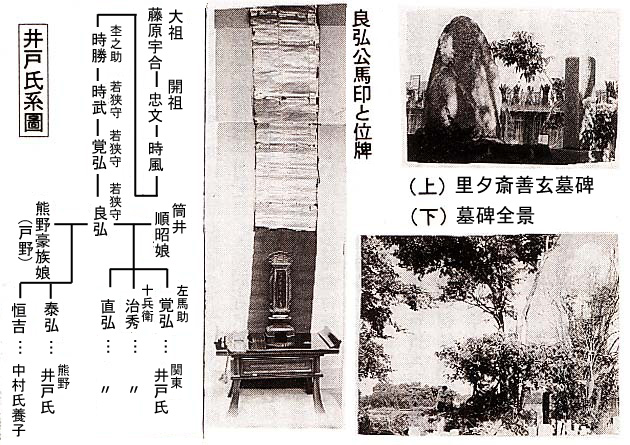�@�c���\�ܔN�i��Z��Z�j�̔N��������ƁA�L�b�Ƃ̍��͂��X�����Ɖ]���鋞�s���L���̑啧�a�Č����i�ޒ��ɁA�����Ƃ̈ɉ����̉��C�H�����}�e���|�Ői�s���Ă����B
�@���������n��ƒz��̖��l�E���Ղ����ɁA�c����N�i��Z�Z�l�j���璅�H���ꂽ���̕F���̈�ɏ�Ƌ��ɁA���U���̓��̕t��ƂȂ鎖�͕S�����m�������B
�u�Â͋x�����A�ɉ��삱����l�w���̔鑠�̏�v
�@�Ɠ��{��̍��Ί_�̌��łȕ��R�邪�o�����āA�ɉ�̐l�X����������B
�@�Ĕ����ɂȂ�ƁA���s�ԍ�i*1�j�̓����ŕ���ȗ]�����y����ł����א�H�ւ��a�ɐN���ꂽ�B���[�ւƓ������A���q�E�������}�O�l�\�ꖜ�̑��ƂȂ��Đ��ɂƂ��߂��Ă��Ă��A������ւ͍s���Ȃ������B
�@���[�ւ́A�l�G�t�H�̕ς�ڂɂ́u��������ɗ����v�ƗH�ւɏ�����Ă����悤���B���n��͉���ȗ��[�ւ��A�����̓��ɂ����Ă͉����̗v��ʒm�Ȃ����ɁA�}�������ɕ������B������H�ւ̕a���Ɏ����A�߂����̎v���o�����A�݂ɂ��ꂩ���̐��̗�����Ă��������̗�������ɂ��݂ʂꂽ�B�H�ւ́A������\���A���s�O���ԉ����̎��@�Ŏ����B���N���\���B
�@�����ėH�ւ̎���m�����o�O��́A�Ăэ]�ˈڏZ�������߂��B���������[�ւ͑��ς炸�u�킵�͑�a�̗[�邪�D�����Ⴉ��v�Ə��đ���ɂȂ�Ȃ������B����͖��m�̉]���u���X��ɂ̗��}��҂��A�[�X�Ō�̋߂Â��̂���ԁv�����߂����Ă����̂��낤�B
�i*1�j�ԉ����̌�L���B�ԉ����́A���݂̋��s������͌����ʎO���B�ԍ㒬�́A���s�s������[���B
�i�Q�j��쒷���A���������A����
�@�₪�Čc���\�Z�N�i��Z���j�̔N�ɓ���ƁA�₩�ɏ㗌�����ƍN���G���������u�Ăы��ނ悤�Ȃ�v�Ɗo������߂��B
�@�����m�������������A���������A���K���i*1�j��q�����̑喼��́A�a�闄�N��������āA�����ɑ̖ʂ����܂��A���A���̐l�X�����S�������B
�@�ނ炪���݂ł������A�L�b�Ƃ͈��ׂ������낤�ɁA���̏t�A��Ð�쒷�����v���i*2�j�A�����ĘZ���ɂȂ�Ɛ������a�ɕ����B
�@�����m�����G���͋����đ�펛�̋`�~�ɉF������������A�a���͏d���Ȃ����ł���B
�@�����Ĉ��[�A�������a���ɑ��q�������A����̘_������o���Č��ɂ́A
�u�O�c���ƌ��̕a���d���ƕ����A�i���A�������j�����ɎQ�サ�����A�����łɒU�[�ɔ��������ƌ��́A
�w���}�A���ɗՂ݁A�g��[���i���Ɓj�a�A�ЂƂ��ɏG���̂��Ƃ����ݐ\���h�ƌJ�Ԃ��ꂽ�B�Ȍ�킵�́A��ɁA���̖{�i�_��j��S�̎x���ɐs���ė������A��������Ȃ��Ɍ�����B�[���n�ǂ���āA�b�߂�S��������A���X�����肢�\�����x
�@�Ɨ܂𗬂��ꂽ�B
�@�R�����̍��́A�Γc�����i�Γc�O���j�߂������āA�{��ǂޏ��ł͂Ȃ��������A���ɂȂ��ēǂ�Ō����
�w�ȂĘZ�ڂ̌ǂ�����ׂ��i���j��߂ɗՂ�ŒD���ׂ��炸�B�N�q�l���B�N�q�l�Ȃ�i*3�j�x
�@�Ƃ̏͂��S�ɒɂ������݂�B����G�������A�͂��Z�\�ܖ��̐g��ɗ�����ꂽ�̂����āA���}�q���̎҂̓������A��Ƃ��X����v���������ƌ��A�Μ��Ɋ����ʁB
�@���̏�͉ƍN�����A�ǂ����N�q�ł����Ė]�������̂���B�v
�@�Ƃ��݂��ݒQ���Ȃ��琢������B�i*4�j
�i*1�j�����̂悵�Ȃ��B1576�`1613�B�I�ɍ��I�B�˂̏���ˎ�B��쒷���̒��j�B���V��18�N�i1590�N�j�Ɍ�k���������i���c������j�ɎQ���B���\�E�c���̖��ɂ����ƂƂ��ɌR�𗦂��ďo�w�A�c��2�N�i1597�N�j�ɉU�R�`��i���݂̉U�R�L��s���j���ď邵�A����B�����\2�N�i1593�N�j�ɕ��ƂƂ��ɍb�㍑�{���i�R�����b�{�s�j��^����ꂽ�B���\4�N�i1595�N�j�A�֔��E�L�b�G���̎��r�ɘA�����A�\�o�i�ΐ쌧�����j�ɔz���B�O�c���Ƃ̂Ƃ�Ȃ��������Ă܂��Ȃ����A�B���c��3�N�i1598�N�j8���̏G�g�v��́A���N�łƂ��ɐ�������������E���������畐�f�h�ɗ^���A�ܕ�s�̕����h�E�Γc�O����ƑΗ��B�c��4�N�i1599�N�j�̑O�c���Ɩv��ɂ͕����E������Ƌ��ɐΓc�O�����P���B���c��5�N�i1600�N�j9���̊փ����̐킢�ł͓���ƍN�����铌�R�ɑ����A��{�R�t�߂ɕz�w���Ėї��G���A�������ƂȂǂ̐��R�������������B���ɂ͋I�ɍ��a�̎R��37��6���^������B�c��16�N�i1611�N�j�̓����ɂ�����ƍN�ƖL�b�G���̉�k�ŁA���������Ƌ��Ɍx�����s���B�c��18�N�i1613�N�j8��25���ɘa�̎R�Ŏ����B���N38�B�j���������������߁A��̐�쒷�����p�����B�揊�́A�a�̎R���̍���R���n�@�B�a�̎R�s����̑����R��B
�i*2�j�L�b�����̌ܕ�s�̈�l�B�c��16�N�i1611�j4��7���v�B���N65�BChap 2�L�Ƃ̊�2.1�ǍO�F�엎�����Q�ƁB
�i*3�j�Z�ځi�肭�����j�̌ǂƂ́A�������������Ă݂Ȃ��q�ƂȂ������N�B��l���S���Ȃ��āA��p�҂��܂����N�ł��鎞�ɁA���̎ア���N���Ɏ��A��펞�ɗՂ�ł��A�����Ă��̌��͂�D��Ȃ��l�B���������l�����A�N�q�l�i�^�ɑ��h���ׂ��l�j�ł���A�Ɖ]���Ӗ��B�w�_��i�ה��攪�j�x
�i*4�j�c��16�N�i1611�j6��24���v�B���N50�B
�i�R�j�^�c���K�A����
�@�����ĊԂ��Ȃ��A��x�R�̐^�c���ł��u�ƍN�̋S��v�Ƌ����ꂽ���K���v�����A�Ɖ]���]�A��a��~�ɂ������B�i�c��16�N6��4���v�A���N65�j
�@�����m�������[�ւ́A������Ə̂��ꂽ���s�ؗ�ȑ��邪�傫���X�����悤�ȑz���������B�����ƉƍN�߂́u�҂ĂΊC�H�̓��a����v�Ƃ������Ԃ��Ă��邾�낤�A�ƓV�̔��Ɋ������ɈႢ�Ȃ��B
�u�^�c���K�a���S���Ȃ�ꂽ�v
�@�Ƃ̔ߕF��{�{�̒n�ɗ��ꂽ�̂́A�c���\�Z�N�i��Z���j�̎����ŁA�^�c�ꑰ�Ɠ��������˂̊Ď����ɂ������V�{�s���i*1�j�͂�������R���p�ɂȂ��ď\�Ð��������B
�@�Ɖ]���̂��^�c�ꑰ�ƐV�{���͐[���Ȃ��肪���邩�炾�B���Ȃ킿�A���}�ݐ����ɁA���ɐl���Ƃ��āA����ʼn߂������Ȃ̂ł���B�^�c�K���̐����Ȑl�������āA�N���̍s���͌Z�Ɏd����悤�ɐڂ����Ƃ����B
�@�K���́A�G�g�Ɍ����܂�āA�g�]�܈ʃm���E���q�卲�h�ɔC�����A�L�b�̐��܂ŋ�����A��J�Y���̖����Ȃɂ��ĉƒ���������B���̍K���ɑ��āA�s���͂܂�Œ�̔@�����̉Ƃ�K��ĎG�p���Ƃ߁A�V�Ȃ���傢�ɗ���ɂ��ꂽ�B�K�����܂�
�u���Ȃ��̌����ɂ͉��Ƃ��Ԃ����点�Ă��˂̂��v
�@�ƍ���܂��Ă���A����悭�g���n��h�ɔC�����āA���i�x�����P�j������Ă���B
�@����Ȃ��Ƃ���^�c�i���g��j�Ɩx���i���[��j�̗�����̎�͐e����[�߁A�փ����ɂ͋��ɐ��R�̗E���ƂȂ��ĕ��킵���B���K�͏�c��ŁA����G���Ɩ{�����M��z�낤���āA�O������̑�R����ɒx�ꂳ���Ă���B
�@���P�͈ɐ��p��~��\�����Đ��C��������ƁA�Ï�̍U���ɑ���𗧂āA�������R�������ċ���Ώ\�����̑喼�Ƃ��ĈېV�܂ʼnh�����ɈႢ�Ȃ��B
�@�����Ĕs���A�x���͌F��O�R�匟�̐_������A�^�c�͑��q�E�M�K�Ɖł̕��E�{�������Y�̐s�͂ŁA�������͏��������B
�@��B�̐����́i�x�����P�j�ƋI�B��x�R�i�^�c���K�j�ŋ��ɉƍN�݂Ȃ���
�u���}�Ƃ̋`�ɔw���A�N�q���铹�ɔ������j�������܂ł��h���锤�͂Ȃ��B�K�����߂ĖS�ڂ����ɒu�����̂��v
�@�Ɠl�u�ɔR�������Ă����̂ɁA�ɂ�������Î��P�A���x�͏��K�������������͖̂L�b�ɂƂ��đ傫�ȒɎ�ł������B
�i*1�j���� �䂫�Ƃ��B1596�`1645�B�����͖x�����O�B�I�ɍ��V�{���E�x�����P�i*1-1�j�̒��j�i�Z�j�A�܂��͒�Ƃ��j�B���`�i�������Y�`�Ƃ̓���j�̏\�j�E�V�{�s�Ƃ�c�Ƃ���B��̖��͎ዷ��B���L�b�G�g���V���ꂷ��O�ォ�炻�̉Ɛb�ƂȂ�A�փ����̐킢�ł͐��R�ɑ����ĉ��ՁA�v���B�����K�����I�ɍ��a�̎R���ɕ�������ƁA�s����500�ŏ���������ꂽ���A�ҋ��ɕs�������ڂ��ďo�z�B�����̖��ł́A���̉̂���300�l�𗦂��đ�쎡�[�̊�R�ƂȂ�A����Ɉɓ������̕����ɑ������B���Ă̐w�̓V�����E���R�̐킢�ȂǂŊ��A�I�B�Ꝅ��������邱�Ƃɂ���ċ���E���Ƃ����������Ă���B�����邪���邷��ƈ�U���ꂽ���̂́A��a���ŏ��q�d���R�ɕ߂炦���ĕߗ��ɁB���̌�A�O��̖x�����v�i����A�܂��͉��Ƃ��j�̐�P�~�o�̌��ɂ��͖ƁB�ɐ����Ôˎ�E�������Ղ̉Ɛb�ƂȂ����Ƃ����B�܂��A�ِ��ɂ͑�a�����c�ˎ�E�Ћˎ���70�Ŏd�����Ƃ��`���B
�i*1-1�j�x�����P�i�ق�̂��������悵�j�B1549�`1615�B����Ƃ��B���[��B�I�ɐV�{�̎�B�x�����͌F��V�{�ʓ����X���߂��ƕ��ŁA�V�{�𒆐S��2��7000 �i�����6���j�̒n���x�z���������ł������B�����P�͓V��13�N�i1585�j�ɖL�b�G�g�ɑ����Ė{�̂����g����A���N�̖��ɍۂ��Ă͐��R�𗦂��ď]�R�A�W�B�U�߂ȂǂɊ����B���c��5�N�i1600�j�A�փ����̖����N��Ƌ`���ł����S�×��ƂƂ��ɐ��R�ɑ����Ĉɐ��N�U���邪�A������͂̔s������d�B����V�{������R�ɍU�ߗ��Ƃ��ꏊ�̂������A�I�ɉ��c����孋������B���̂�������Ĕ�㍑��̉��������Ɏd��2000��m�s���A�F�y���a�����A�c��14�N�i1609�j�ɓ��n�Ŗv�����Ƃ����B�������A�v�N�ɂ��Ă͌��a���N�i1615�j��������B(http://wolfpac.press.ne.jp/daimyo06.html)
�i�S�j�V�{�s���A�L�b�G������U����
�@�̂���^�c�Ƃɂ͑t�m�������`���A�F��R���B���҂ݏo�����Ɖ]���E�@����X�`���A���̓����E���B���E�q��́A���K�̖������A�]�ˁA���̓��Â���f�Ȃ��������Ă����B
�@�����孋��������N���d�˂閈�ɁA���̐����͋ꂵ���A���̍��͕Č\�ł͂ƂĂ����肸�A�Ɛb�B�͋ߍx�Ŏ������A�^�c�R���s�����ē��X���x���Ă����悤���B
�@�s�����^�c����K�˂��̂͘Z���̖��ŁA��K���́A�Ē��ƎR�ł��ĂȂ��A��ӂ��܂Ō�荇�����Ɖ]���B���ɗD�ꂽ��ؗ��R�w�҂����ɁA���̈�u���p����������Ȃ��������͂Ȃ��B
�@�����čs�������̋A��ɑ�a�̗��[�ւ�K�˂��̂́A�邩�ɏG������
�u���邷��Ύዷ��ɔC���A�喼�i�Ƃ��Ĉ����v
�@�Ƃ̓��ӂ��Ă����̂ŁA���c��X�ዷ��𖼏���Ă������[�ւ̗�������Ƌ��ɁA����b�������������̂��낤�B
�@�s���Ɨ��[�ւ̐e���͑O�q�����悤�Ɂi*1�j�\�N���̉��ŁA�s���͗��[�ւ̐l���ɓ��ꂳ�������Ă�������A�{�{�ɋ߂��n�ɕ邷�O�i���[�ւ̎q�j�Ƃ͌Z��̂悤�Ȓ��������B
�@����Lj������ɂ��āA���[�ւ̋������@�����s���́u�O�ꑰ�̕��a��j��悤�Ȏ��͌����Ă��ʁv�ƖāA�ʂ���������炵���B
�i*1�jChap2�L�Ƃ̊�2.3��a�S�����Q�ƁB
�i�T�j���[�ւ̈⌾�@
�@������߂��镗�_����i�Ƌ}�������钆�ɁA�c�i�\���N�i��Z���j�̐V�N���K��A���[�ւ͔��\�˂ɂȂ����B
�@��N�̂悤�ɔN��ɂ���ė����O��Ƃ�P�g��Ɉ͂܂�āA�̂ǂ��ȏ����𗁂тȂ���A�䂩��̋����䗅��˂̎ᐅ�ɐg�𐴂߁A����_�Ђւ̏��w�����܂����B
�@���ꂩ��C���悭�N�h�������������A�����������̂��B�R�Ƃ����ʎ��Řb���n�߂��B
�u�v����ꡁX�Ɣ��\�N�̒����������悭���������čڂ������̂�ƁA�_���Ɋ��ӂ��鑼�͂Ȃ����A������̌�������B���C�ȊԂɁA���������Ă��鎖�����A���Ȃ���Ɍ���Ēu�����B��������Ƌ��Ɏ��߂Ēu���Ă���B
�@�߂����V���O�N�i��O�l�j�߂̍A��a���苽�ɐ����������킵�́A�c��������
�w�t���_���̐��n�ɎY�ꂽ�҂́A
�@���ɐ_���сA��c���h���A�������O�k�Ƃ��āB
�@�܂��A����ɂ��܂�����ɂ��ޑ�a���m�Ƃ��āB
�@���X����̋Ƃɗ�݂��A����̂����Ȃ݂�Y�ꂸ�A���̈����m��L�ׂ̐l���ƂȂ�x
�@�ƌ������b����ꂽ�B
�@�����ĕ��̓��ɏA���ẮA����_�Ђ̊y���E�ł������ϐ���傩��\�y���A�����A���ԁA�A�̂ɏA���ẮA����̗������������m�@�Փa�̈�Ԓ�q�ł���R��@��a�Ɏt�d����
�u����������A�a�h�Î���|�Ƃ��A�������̂Ƃ��т���Ƃ���v
�@�Ƌ������Č��r�������肶��B
�i�U�j���[�ւ̈⌾�A
�@�R���Ȃ���A������������������t�̗����̒������ɁA�S�Ȃ炸���C���̍J���n�炴��Ȃ������̂́A���Ȃ�����悭�����ċ��낤�B
�@����Ȓ��ɁA�v�炸���M�����́u�V���z���v�̎P���ɉ������A���G�a�̗^�͂ƂȂ��Đ�w�����ɂ��A�ނ̐����N�b�̋`���d�鉤���v�z�Ɋ������u���������ɂ���v�ƌ��ӂ����B
�@�c�O�Ȃ���A���̕��^�͂��Ȃ��u��E���v�̉����ɂ܂݂�錋�ʂƂ͂Ȃ��Ă��A�N�q�l�Ƌ��M���ɂ͕ς�Ȃ��A�R���ƂȂ��ČF��ɗ����Ȃ������ɐS�ɂ������̂�
�w���m�̉R���Ɖ]���A�m�̉R�͕��ւƐ����B����ƂĕS���͉��䂫���̂ł����邼�x
�@�ƈ₳�ꂽ���t�ł���B
�@�킵���g���m�͈ꓹ���Q�l����A��x�Ɣe���͕��܂��h�ƁA�{�d���������A�����Ɏ������̂́A�Ђ�������Ƃ̐������ʂ��ׂł������̂�B
�@�M�����͐��ɕs���o�̓V�ˎ��Ƃ͉]���A���̂߂������e���͂킪���̂ɂ͋����ꂴ����̂ł������B
�@�����������G�g�́A�����܂Őb��������ČÍ��ƕ��̉p�Y�ƂȂ�A�V���ꂵ���̂͌����Ɖ]����B�������֔��ƂȂ��ĈȌ�́A���F�Ɩ������×~�̂܂܂ɁA�������Ƃ����v���ʔӔN�ł������B
�@�����ĔނɎd���đ�V�M���ƂȂ�A�V����̗��`�҂�Ǝ^����ꂽ�ƍN���A���悾����
�w�V���͔n��Ő������Ă��A�n��Ŏ��߂邱�Ƃ͂ł��ʁB�V���̐l�S�����ߓ��Ă����^�̓V���l�Ȃ�x
�@�Ə̂����ƂāA���̐S��̔ڗ͒f���ČN�q�l�Ƃ͉]���ʁB�₪�Ă͐M���ȏ�̔e���ƂȂ�A��̎q��S�ڂ��A���삳�����x�z���Ɏ��߁A�����A�����̂߂������@���A�Ȃ̌����Ђ���𗧂Ă�Ƃ����]�ނ��낤�B
�@�o�O��͔ނ���N�Ƃ������̂ɁA�ۉ��Ȃ����̖��ɏ]�킴��ʂ��A����͕��̕������������A�����ċ{�d���͂����A��ɖ�ɍ݂��ĉҋƂɗ�݁g�����Ɛ����h���|�Ƃ���B�v
�i�V�j���[�ւ̈⌾�B
�@���[�ւ́A���N�Ŕ��\�Ƃ͎v���ʋC���œ�l������
�u�O��B���Ȃ��͌F��ŁA�킵�̑n�Ƃ̎u���p���ŁA���l�ɖ𗧂F���ˉƂ�z���̂���B�����čP�g�́A���c��X�̖���܂ق�̒n�ɍ݂��āA�����Ƃ̎k�q�ƂȂ�A��_�ꑰ�̔ɉh�ɐs���Ȃ�����A�{��������ˉƂ̕������낵�����ނ��v
�@�Ɩ����ē�l�ɐ��X�̈�i���I��ƁA���͂�v���c�����Ƃ͂Ȃ��A�Ɖ]�����ʎ���
�u���ĕ���̓��ɂ��āA���͔\�ƒ����ɋ��߂����A��������݂̂ɂ�����炸�A�A�́A���ԁA�����A���悢����ɂ��悱�̓��͍L�傶��A������̍D���ɂ����B
�@�Ȃ�ǁA�f���Č��͂▼���ɛZ�т��A�^�́g��тƂ��сh�ɊJ�Ⴗ�鎖�B����ɂ͉�Ƃ̉ƕ�ł���g�T�䓛�̍��풃�q�h���g�V����̈�˒��q�h�Ɛ��ɍL�߂Ă��ꂽ�R��@��a��A���̎t�E���x���m�a�̐��Ԃ���������Ɛg�ɂ���̂����������v
�@�����]���Ȃ��痢�[�ւ́A���̒m�Ȃł������R��@�A�G�g���玨�A�@�����̎S�Y�ɂ��B�R�Ƒς������̐l���A�����āA���x���A����������O�̈��̒��m���҂Ƃ͉]���A�V���̖��l��搂��A�喼���������͂��ւ����ނ̐�R���n�̗E���ɏ��鍋���ȍŌ�������^�����B
�u�������Ȃ���A�킵�ɂ͔���ʂ̂��A���x���m�́A���́A���}����O����̘\���������A�Ɖ]�����Ƃ�B���m����҂̏K���Ƃ��āA������ȏ�́A���E�^�D�̌�������o�傪�̐S����B
�@���x�a�́A
�w�̂ђ��̐S�́A���̏����~�ɂ������B�Ƌ��̌��\��H���̒����Ȃǂ͑����̂��́B�Ƃ͉k�炸�A�߂͒g����Ηǂ��A�H�͋Q���˂Ώ[���ł���B
�@�����^�сA�d�����āA�������A���𗧂āA���ɋ����A�l�ɂ��{���A����ۂނ̂݁B
���Ԃ��̂݁@�҂��l�ɁA�R���́@�_�Ԃ̑��́@�t��������B�x
�@�Ɖr�����B
�@���̔ނ��A���}�ɕ�����ꂽ�B������̑��}������A�������R�̒z�������t�A��t�ɗ��ʉ��������̐v�𖽂���ꂽ�͓̂��R�Ƃ��]����B
�@�����܂Łg�̂ђ���h����ނȂ�A�{�d��������ׂ��ł͂Ȃ������Ǝv���B
�@���}�́A���x�����f����A����̋M���⍂�m��̍D�݂ɉ��������������������߁A�Óc�D���ɖ����ď��@����ƒ뉀���̍��s�ȑ喼������n�点���B
�@����Lj�N��ɂ́A���߂ɂ������x�̒��j�E�����Ǝ��j�E�����������Ă���B��������B�̍א쒉���ɁA��������Â̊��������ɁA�ĔC���������̂͌���������炾�낤�B
�@���̎����悭���L���āA���Ȃ���͂����܂Ŗ�ɂ����Ĉ�|�ɓO���A������Ƃ炷���z�̉��ɁA�厩�R�̒��́g��тƂ��сh��g�ɂ���悤�ɂ���B
�@���ꂪ������a�̗H���\�ɂ��ʂ��铹�Ȃ�A�Ƃ킵�͍l���ċ���B�v
�i�W�j���[�ցA����
�@���X�ƌ�����͂�������̈ꌎ�ܓ��̗[���B
�@���[�ւ́A���R�ɒ��ޑ����ȗ��z�Ƌ��ɁA���R�Ɛ����������B
�@���[�ւ̑��V�́A�ꌎ�����A�{�������ŁA�m�Ȃ݂̂ł܂����Â��ꂽ�B���̗҂����L�l�������S�Ȃ��l�́u���ꂪ�̌��喼�̑������v�ƈ⑰�B�������Ɖ]����B
�@����ǂ���͔ނ̈⌾�Łu�֓��̌Z�B�̋{�d�������܂�����ȁv�Ƃ̌��t���������̂��낤�B
�@���̉������A�@�a�勏�m�ȂǂƉ]�����̂łȂ��u���[�֑P���v�̌��ɉ߂��Ȃ��̂����Ă��A���̐l�����Â�A������ł���������q�B���u�������Ɍ��͑����ʁv�Ǝ^����l�������B
�g�l�͓Ƃ萶��āA��l�����Ǝ��ʁB���{������̂����܂��������ǂ��h
�@�Ɖ]���̂����[�ւ̈�u�ł������͉̂]���܂ł��Ȃ��B
�i�X�j�{��������K�˂�
�@�������N�i����Z�j�̏H�A�n�߂āA��ˎ������̑c�E�ǍO���̕�肪����{��������K�˂��B
�@�ޗnj��Y��S�X�{���̓����ɂ���u�_���V�c�̐��ցv�Ɖ]����a����̎R�ӂ̓��̂قƂ�ŁA�����͓ޗǁ`�������������Ɖ]���B
�@�{���͏\��ʊϐ����A����ɔ@���A�O�@��t�Ŗ������N�܂œ��X����{����O�傪�ނ��Ă����炵���B
�@�����ɂ���
�u��ˎዷ��A�Y���i���̊o�O���H�j�̌ܗ֓��ƈʔv�͑�������ɂ���v
�@�Ɩ��L����Ă��邪�A�������N�ɍГ�ɂ���Đ������āA�{�������厛�ȂǂɈڂ��ꂽ�B���݂́A�����Ȃ��A�V���`�c���̐Γ��̗ї����钆�ɁA�ǍO���̔����Ђ̐Ղɒ��܂��Ă���B
�@���a�����Ɍ���������ŁA���炭�⌾�ɂ���āg���[�֑P���h�Ƃ����L�����ؔ肪�Ό��Ƌ��ɋ����ʂĂ��̂���u����ɔE�т��A�������̕������Ă�ꂽ���̂��낤�B
�@�l�ӂ͂������ɗI��Ȓ��]�ŁA�퍑�喼�̉��Ï�i*1�j�ɂӂ��킵���u�����ȂÂ��@�_����Ȃ�@���ɑ�a���@���킵�i*2�j�v�̋�̒ʂ�ł���B
�@�ē����Ă��ꂽ��a��ˎ��̒����E�������ێ��͎��̂��Ƃ������B
�i*1�j�_���ł͕�̂��Ƃ����Ï�i�������j�Ɖ]���B
�i*2�j�`�͍��̂܂ق�@�����ȂÂ��@�_�@�R�������@�`������킵�i���}�g�^�P���j
�i�P�O�j���̌�̈�ˈꑰ�̗���
�@�퍑���㖖�����瓿��̐��ƂȂ鍠�B
�@�n���̑喼�����́A���̌������c���ׁA�������i���u���鐢�ɁA��ˈꑰ����B�^�c�Ƃ̔@���A���̎q���֓��n���ɑ���A���F��ɂ��q�����c���B
�@�o���{��̒n�A��a�ɂ��̖��q�E���Y�E�q����ꑰ�̕M���ƘV�E�������ɑ������̂́A��ˉƂ̕�ɖ���c��̕������Ƃ��ړI�ł͂Ȃ��������A�ƍl������B
�@����Ē������Y�E�q��i��_�P�g�j�̐��������ĐΏ�ɋ��Z���A�ƘV�̒����Ƃ́u���c�����v�ɋ����ڂ����ƂƂȂ����B
�@���̏Ƃ��ėǍO�����A�Z�A�����A��A����A�S�C�꒚�A���l���l�Ǝ���̏����i�̓���i�̎�̂̋L�^���c����̂́A���̎���ɂ��U�킵�A���݂͌n�}�ƍ����n�Ɏh���q�̋�������̍������̏����݂̂ƂȂ�B
�@���̌�̎q���́A�̒n�������Ƃ̎x�z���ƂȂ�A�����l�Ƃ��Ė����ѓ��͈ێ����A�Ώ�n�̂����߂��B���̒��ŋ��E������L�i��_�D���j�́A��Ƃ����t�̋g�v��U�Ɋw�сA�w�l�Ȑ���g�ɕt���Č�a��Ŗ��𐬂��A���̕w�l���̒Ñ����V���̎n�܂�Ɋ|���荇���Ƃ̉]���`��������A���炭�F�삩�瑗���ė����i�̔̔��ɂ����������炵���B
�@���̌�A�\���E�莟�Y�ɂ���ď��a�ܔN�i���O�Z�j�ɓ����ǍO���̖������ꂽ�i���͔p���̖{�������Ղɕ�W�������{���c�݁A���̌�̑����ɂ��A����\�ܔN�i���܁Z�j�ɐΔ�������B���Z�\��N�i��㔪�Z�j�㌎�ފ݂ɁA�O�S�\����̋��{���c�݁A�����Ɏ���B
�@�c��̋��{�����Ɏp�������Ɋ��ӂ��鏈�ɂ��āA�l�S�N���r�₦�Ă����F���ˎ��ƍĉ�o�����̂́A��ˎ����u�T�䓛�v�̎��M�ɍۂ��āA���X�Ȃ�ʂ��w�͂̎����ƁA�����đc��̌䍰�̓����Ɛ[���������鏈�ł���A���߂Ĉ�ˎ��̗��j�T���̌䑢�w�ɐS���犴�ӂ��鎟��ł���܂��B
�����\�N�ꌎ�����@���ˌ�������
�ዷ��`�O�\����̑��@�����@����