�@�V���\�N�i��ܔ���j�Z���\����A���G�͓������i*1�j���~��Ēj�R���牺���H�ɖ{�w���ڂ��ƎR��A�����̕���P�ނ����A���Ə������i*2�j�����_�Ƃ����B�����X����ːi���ė���G���R��̊X�͂���𗬂��~�����쉈���Ɍ}��������ɕς����̂ł���B
�@�l�I�̌R�t�E�ē����O��
�u�l���̏G�g�R�ɎO���̈���x�̕��͂Ō���ނ͕̂s���B�����͈ꎞ�������ċߍ]�e�n�ɎU�݂��Ėk�ɔ����Ă���E���E���t�ȉ��ܐ�̕��ƍ������A��{�A�T�R��ɂ���Đ키�ׂ��ł���v
�@�Ɨ͐����Ă����G��
�u���s���̒������������͏o���ʁv
�@�ƕ����Ȃ������S���͏[���@������B
�u�����A�r�ؑ��d��ꑰ�����݂ł�������v
�@�Ɠ��S�ɒQ���Ă����ɈႢ�Ȃ��B
�@�����ĘZ���\�O���A����̓��͒����狭���J�������B
�@���G�͈��y��������t��ɋ}���Q��̋}�g�𑖂点���B�J�̒��������H���珟�����̑O���Ɉʒu�����V�ˁi*3�j�ɖ{�w��i�߂����A���̔z����
�@�����ɐē��A���A�ēc�A���q�Β���̋ߍ]���A
�@�E���V���R�[�ɂ͏��c�A���͂̒O�g���Ɉɐ��A�z�K�A��q�狌���{����O�A
�@�����ɂ͒Óc�A����炪���쉈���Ɏ����ł߂��B
�@���G�{�w�ɂ͓��䂩��A�������c�`�܂��\�����Ƃ��čT���A���̑����͈ꖜ�Z��]�Ɠ`����B���G���ł����݂Ƃ���E���E���q���t�ȉ��O��̐��s�̎p�������Ȃ������̂́A���Ƃ��Ă��ɂ��܂�ĂȂ�Ȃ��B
�@����ɑ���G�g�R�́A
�@�����ɍ��R�A����A�x�B
�@�E�������ɒr�c�A�����A�ؑ��B
�@�����V���R�[�ɂ͏G���A���c���z�w�A
�@�����ďG�g�{�w�A�I�J�A�O�H�A
�@�a�R�͐M�F�ŁA�`�R�O�����]���т����藼���X���߂Ă����B
�@���G�Ɛe���̂������g�c�����������̓��ɉ����H����R��߂��܂ŗ��Ċϐ킵�Ă���̂͒�̓��ӂ��u���Ƃ����G�������Ă���ʂ��v�Ɛ_�ɋF��C�����������낤�B
�i*1�j���s�{�����s������R�B���ē�����X���̒��p�n�B���݂͂��̏�����������1���i�����o�C�p�X�j���ʂ�A�����_�̖��O�Ƃ��āw�����������x������B�������A�Ȃ��肭�˂������͂Ȃ����`�̗ǂ����H�B
�i*2�j���傤��イ�����傤�B���s�{�������s�ɏ��݂����B�閼�́A�t�߂̓����Ù��ɗR���B�{�ۂ���я��c���䂪1992�N(����4�N)�ɏ�����������Ƃ��Đ������ꂽ�B
�i*3�j��V��(����Õ��Q)�́A���s�{��R�蒬�̓��k�[�Ɉʒu����B�T���g���[���s�r�[���H��̗���ɂ���A��V�ˁi����Õ��Q�j�ƌ��G�{�w�Ղ̕W��������B
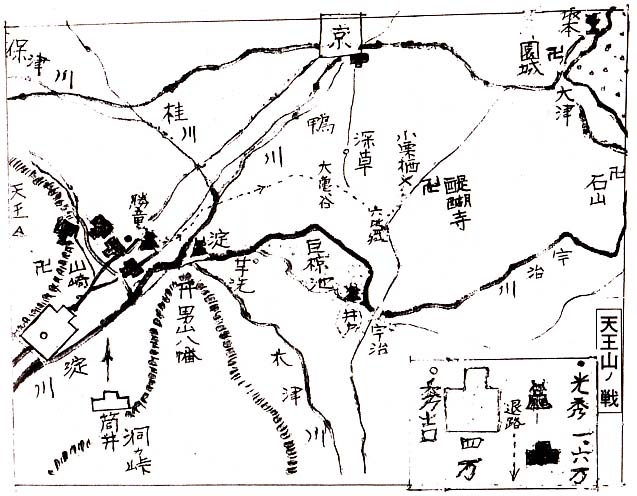
�i�Q�j�J��
�@��[����ꂽ�̂͌ߌ�l���߂��V���R���ʂ������Ɖ]����B��͂�V���R����ǂ����E����d�v�n�_�ƂȂ����B�Ǖ��ł͂����Ă����R�ɒn�̗���I�ׂ����q�������ɁA�����D�c�R�̒��ł��u���q�̓S�C���v�Œm��ꂽ���s�O�炪�E���E���t�ɗ������ĊX�����������V���R�Ɍ��w��z���ċ���ΐ�ǂ͑傫���ς����ɈႢ�Ȃ��B
�@����͐킳���Œm��ꂽ�ē������������킳�Ԃ�ō��R�w�������ėD�����������B�ɐ��疋�{����O���\�z�O�ȕ�����������̂�
�u���̈��ɏ��ĂĂя��R�`�������Ɍ}���Ė��{�ċ��������o����v
�@�Ɖ]�����Ҋ����炾�낤�B
�@����̕s�����������G�g�́A��E�G���ƍ��c�A�x�R��
�u���Ƃ��Ă��V���R���U�ߎ��v
�@�Ǝ��B���A�{�w�ꖜ�̐��s�̂��ׂĂ��R���襘H�ɓ�����B����Ƌ��ɉE���̑����̖ҏ��B��
�u��C�ɉ~������˔j���ė��쉈���ɓG�̍������͂���v
�@�ƌ���B�ҏ��E�r�c�����Ă�������ׂ炪���������Đē����ɏP�����������B
�@���̒��A���䏇�c�́A�G�g�A���G����
�u�����Ɩ�����A�M�F�l�ɏ]���ė���ۂɐw�����f�Ȃ��~�U����v
�@�ƌ�������Ă����B���������̎��A���䐨�ꖜ����������A�˔@�����n�͂��ďG�g�{���̔w���˂��A�҂��\���Ă����ǍO��͗E��Ɍĉ����A��ǂ͈�ς����낤�B
�@�c�O�Ȃ�����ɓ���̔~���̔n��͎p�������Ȃ������B
�i�R�j���q���G�A��������ɑނ�
���ɖ����ʐē����͕�͂���ĕ���n�߂�B�\�����ƂȂ������q�̖ҏ��E���c�`�܂�����̉������ۂ��������ĖҔ�����W�J���A��ǂ͈�i��ނ��J�Ԃ��B�������A�R�m��̖��q�̗E���E���c���Y���q��炪���������ׂɁA���ɓV���R�͏G�g���̎�ɋA���A�j�ǂ͂�������n�܂����B
�@�����Ԃɂ��Ė��q�̑����ŕ���������Ă����ē��A���c�����������o���ĕ��ꂽ�B����O�̌�q�������{�w�ɋ}�g�𑖂点
�u�킳�͑�����܂łł�����B�g���͎c�鏫�m�Ƌ��ɓG�w�ɓ˓����ē����d��Γa�ɂ͈ꍏ�������������ɑނ���}���v���܂��悤�v
�@�Ɛi������B
�@���G��
�u���Ȃ��ɂ��v
�@�Ǝc����{���̑S�͂𓊂��čŌ�̈������s����Ƃ������A�V�b�E��c�ѓ�����̌��_�ɂ�������A
�u������Âȓa�ɂ����ʂ��U���A�Ⴆ����͔j��Ă����y�A��{�A�T�R�ɂ͌��t�a�n�ߌܐ�̖��������݂ł���A�ċ��͌����ĕs�\�ł͂���܂��ʁA�����͐悸�������Ɉڂ��܂��v
�@�Ɩ����������g���������B
�i�S�j���q���G�A������
�@���G���v�������ď�ɑނ������A���q�R�̓����͎O����z�����҂�������Ζ��ɋ߂��ނƋ��ɓ��邵�������͐�ɖ������A�@���Ɏ��͂�s���Ă�����͎��Ԃ̖��Ǝv��ꂽ�B
�@�Q�����R�c���J����A�ߍ]���ƍ������Đ�Lj����v�鎖�ƂȂ�B���G���a�������q�A���q�Β���Ɛ��\�R�Ƌ��ɔ邩�ɏ���o���̂͂܂��G�g�����������͂ޑO�������B�G�g���͏������Ƃ͉]���A���m�̎��҂͎O��O�S�A���҂͐��m�炸�Ɖ]������A��i�M���j���E�������G�ɖ��q�̏��m�͂����܂Œ��߂�s������ŁA��]���̋������Â��B
�@����o�����G�̈�s�͋v����̊ԓ��`���ɕ����A�[����T�J��k�サ�ĘZ�n���ɓ��������A���������玵���߂��Ö�̉J�����s�ɔ�J���ނ������Ă����ɈႢ�Ȃ��B�R���ނ���������ڂƕ@�̐�ɂ���F�����ɓ���A�ǍO���q�͕K������͂������Ə�ŋC�͂�{�킹�����낤�B�����ė������ɉF���썶�݂̋ߓ���n������Đ��c�ɒ��s�����ɈႢ�Ȃ��B������}��m���Ĉ��y�������t�ȉ��O��̏��m�ƍ����ł����낤�B
�@����njN�q�̌��G�͔s��̉Q���Ɉ�ˈꑰ���������ދC�ɂȂꂸ�A�Z�n�����瓹�����ɂƂ菬�I���Ɍ������B����͐l�͂̋y�ʓV�^�̐s���鏈�A�Ɖ]����������܂��B
�@�`���ł��ǍO�琔�S��ꠓ���ő҂���тĂ���̂��@�����A���G�͗₽�����_�̑���܂܂ɉF����푺�̏��I���ɓ������B�����{�̎БO�Ő_������Ɣ�ꂫ�����ܑ̂ɕڑł��ē��@�@�{�o���̗��̒|���ɂ������������B
�@�܂�����̒��̏��������鏬��̔Ȃ�ŁA���l���ň�ׂ�����ƖԂ��Ă����y���E�����q�̌J��o�����|�����^�������Z�̘e�̌��Ԃ��牡����[���т����B
�i�T�j���q���G�̍Ō�
�@�b���͏��̒ɂ݂ɑς��Ȃ���n���}�����Ă������G���₪�ė͐s���ė��n�����B�������ߐb�Ɉ͂܂�Ȃ���Ō�̋C�͂��ӂ�i��Ɩ��S���ł̎����ɕM���������Ǝv����B
�@���t��喳��
�@�哹�͐S���ɓO��
�@�\�ܔN�̖�
�@�o�ߗ���ꌳ�ɋA��
�u���{�̕��m�̐^�̏��t�͒�Ɏg����哹�ɂ��݂̂ł���A���̎��͂��˂ĐS���ɓO���ċ���A�G�g����Ⴆ��E���̉������������悤�Ɓg��`�e��ł��h�Ɖ]���A�������p���鏈�͂Ȃ��B
�@�Ƃ͉]���A��ƓV�������ׂ̈ɖ𗧂���Ɩz�������\�ܔN�̗��z�����₳�߂āA�H���̐��E�ɋA������K�ꂽ�炵���B�v
�@���̎����c���ƍa�������q��
�u��[�͐[���������Č�����ʂ悤�ɂ���v
�@�Ɩ������B
�@�����ʼnƐb�B�͗܂Ȃ���Ɉ�̂͋߂��̖��̍a�ɖ��߁A���͈ƕ����ŕ��Ŋ��C���ɋ߂��D�c�̈�p�ɖ��߂�B���ꂩ�爽�҂͎�ɏ}���A���҂͍�{����߂������B
�i�U�j���q���t�̍Ō�
�@�\�O���̖锼�A���n����t�ȉ��A�O��̐��s�͈��y���Ă����B���G����́u�R��Ō���v�Ƃ̋}�g���r���œG�ɎՂ��Ēx�ꂽ�ׂł���B��镨���抸���A���c�ɂ��������������A�b��E�ҋ������q�̔s�k��m���Đ��������A�勓���ďP�����������B
�@������ӂ蕥���đ�Âɓ���ƓV���R�ŕ��킵���x�G���炪�u��炶�v�Ƃ��藧���ǂ����Č���ƂȂ����B�L���ȁu�ΐ��n��v�̖���ʂ����܂ꂽ�͍̂����ł���B���̓��A�ނ͗��R�̒��A���i�Β��𓂍�P�l�܂Ŗ�ꗢ�A���n�̖��Z�����ē˔j�����B�G�����Q�����A����̏��Ɉ��n���Ȃ��ŕʂ��������B
�@���Ă̒��ɍȎq�̑҂�{��ɋ킯����ƁA���G�̈��D�����M�d�Ȍ|�p�i�����̂܂Ď�������͍̂��Ƃɑ��Ă��\��Ȃ��Ɩx�G���ɏ��n�����B���̌�ɍŌ�̈���S�c��Ȃ�����Č��G�v�l�ȉ���去������Ɖ^�������ɂ����B����͐M�M�R�ł̏��i�e���Ɣ�ׂ悤���Ȃ��u�₩���ł���A���q�̉ƕ����Â��B
�@�V���\�N�i��ܔ���j�Z���\�l���A���i�ΔȂ��g�ɐ��߂ēy����̒����ł��������q�ꑰ��
�u�Ƃ��͍��A�V�̉��m��@�܌����ȁv
�@�Ɖr���Ă���͂��\�O���ŋ�������������ɖS�ы������B
�@�]�k�Ȃ���A���{�z��j�ɋP�������������������������y�邪�D���ɋA�����̂������ł���B�ɉꂩ��i�k���M�Y�����������������A���̋M�d�Ȉ�i�Ƃ��]���ׂ����̋�����ނ��ނ��Ă������Ă��܂����Ɖ]������_�O�ł���B����Ȕn���a�Ɉɉ����ł�����ꂽ���Ǝv���Η܂��~�܂�Ȃ��B
�i�V�j��˗ǍO�A���
�@�X�ɓ�����A�邩�ɉF�����K�ꂽ���䏇�c�͗ǍO�̒��q�E�o�O�Ƌ��Ɍ��������ĊJ��~���������߂��B
�@����ƗǍO�͎��j�E���G��T��ɂׂ͂点�āA�����ނ�ɂ��̐S����q�ׂ��炵���B
*
�@�{�\���̕ς�m�������A�َ҂͌N�q�l�Ƒ��h���Ă�����G�a�����ɂ���ɂ͕K���[���������ɈႢ�Ȃ��B������Ă킪�s���������߂悤�ƍQ�����n�������B�@�����ĕ�ł����闌�O�̖��S���ɂ����ނ�K�˂�Ɣ��Ɋ��
�u����ɂ͂��ׂĐ^������낤�B�v
�@�ƒ�̈ӌ���璩�b�A�Ў��̒��V���狞�̒��N���̓������v�����ڂ����q�ׂ����
�u�䍑���_���ƌւ�R���͐_�����n�̓V�q�����A��͓V���ɂ��ĕ��͂�q�d�̔e���ɂ���Ė]��ł͂Ȃ�ʂ̂������Ƃ��Ă�������ł���B
�@�M�������H��̉p�Y�ł��鎖�͂悭�����Ă��邪�A���̗��j�Ɠ`�������Ē�̏�ɗ�����Ƃ̖�]������ꂽ�̂͐b�Ƃ��ċ����ׂ��炴�邱�ƂŁA���邩�Y�ݔ��������Ɂg��`�e��ł��h�Ɨ܂�ۂ�ł����Ւv�����B
�D�S�m��ʁ@�҂͉��Ƃ��@�]��Ή]���A�g�����ɂ��܂��A�������ɂ��܂��B
�@���̋��������A����Ȃ��炱��͎��̕��������t�Ȏ�N�E�@�����������̂Ɠ����Ŏ�E���Ɖ]���Ɛb�Ƃ��Ă͑�߂�N�������̂ŁA���˂Ă�莖�����A�̍ۂɂ͐b����S�����ē������A�ؕ�����o������߂Ă����Ƃ̂��ƁB
�@�Ƃ��낪�A���t���n�ߏd�b���
�w�a�������܂Ŏ��������Ȃ�َҋ����������d��B�Ȃ�ǁA���̐����Ȃ��S���ȂĈ��������ׁ̈A�V�������ׂ̈ɉ����ɂ��ނ��ʐV�����V���l���߂����̂��^�̑�`�Ɖ]�����̂ł͂���܂��ʂ��B
�@�ǂ������S�����������ꎖ�̐��ۂ͓V�ɔC���āA�v���̂܂܂�邾����蔲���g�������炸��s������h���������ɕ��������Ēn���̉ʂ܂ł����v���܂��傤�B�x
�@�Ɨ܂Ȃ���ɂ�����������Ďv�����������悶��B
�@�Y������ʓV���O�N�i����܁j�H�A�O�g�̕ی���Ŕg����ꑰ�ɋ\����A�㎀�Ɉꐶ���w���ł��Ȃ��Ɂg��l�̓V���z�������������ɂ͑卑�͖����ł��ꍑ�̎�Ȃ�K���h�Ɩ����Ƃ͍����Y��Ă͋���ʁB
�@�ǂ��ł��낤�Ƒ��q�B�ׂ̈ɂ��g�Ɛ��������ɂ��Ă͖Ⴆ�܂����B�v
�@�Ɛ^���f�I���ꂽ�̂ɓ����g�l���ӋC�Ɋ����h�Ɖ�����������ł���B
�@����ƌ��G���͗܂����点�A���������グ������̖ї��A������a�ւ̎��̂悤�ȏ���������ꂽ�B
�u�����Ɣ�����ȂČ��シ�B���x�G�g������ɂė��\����āA���R������o���A�ї��Ƌ��Ɍ�ΐw�̗R�A���ɒ���̎���Ɍ�B
�@�R��Ό��G�A�ߔN�̐M���̐U���ɓ{��A������A�{�\���ɉ��ĐM�����q���n���A�f����B����B�c�c�����ɏ��R�{�ӂ��グ����̏��A��c����ɉ߂�����낵�����I�ɗa����ׂ����̂Ȃ�c�c�v
�@�����Đ��X�̐��헼��������A�L���Ȗ��q���C�ɂ��������ĖႢ�A�t�����킵�đO�r���j���K���������ċ������B
�@�܂����y�U����̏\���ɂ́A��������Ώ��R�̓��|�������A�`���������
�u����悭�㗌�̍ۂɂ́A�g�����R�ɔC���āA����ɒ����ȑ������{���J�݂��ēV���ו���������v
�@�Ƃ̕ԏ����͂����R�ɂďG�g�Ƃ͋����̍���������Ƃ��A�����ċ����̂Ɂc�B�R��ɓV�^�������A��\�]�N�̒m�F�ł������א�ꑰ��g���喼�̒���A���R�A�r�c����Őh�_�����ɂ����F�Ɍ����Ă��A�ʂ͑�a�l�\���̑��ɔC����ꂽ�M�a�ɂ܂Ŕw����悤�Ƃ́c�\�H���}����g����ɂ͎v�������ʂ��Ƃł������B
*
�@�ƌ���f���悤�ɉk�炵���̂ŁA�O�\���̏��c�͑����Ȃ���āA�ꌾ�̕Ԃ����t���Ȃ������Ɖ]���B�i�W�j��˗ǍO�A�F��ɗ�����
�@�R���ǍO�͂���ȏ�͉����]�킸
�u�c�c�Ƃ͉]���V�͎��Ƃ��Ĕ��Ȍv�炢���������̂͊����̗��j�̎������ʂ�ɂĖ}�v�̐g�̋y�т����ʏ�����v
�@�ƙꂫ�A�n�����Ɠ��Ђ����Ɗ��ɔ��͗����ĎR���p�ƂȂ��ċ����B
�u����͌��͂ɓ����A�ςɉ����ď��R�鉺�͋����Ă����̐ӂ�ʂ̂��K�킵�ł���A���x�̂��Ƃ����ׂĂ͌��G�a�̓ƒf�Ƃ��ď�����悤�B����͕S�����m�̏�ʼn߂������A���S���œ�������g�������q�h�Ɖ��߂�ꂽ���G���ɏK���g�����g���[�đP���h�ƍ����B�Ⴆ���l�����Ɣl�낤�Ɛَ҂̌��ɑ��鑸�h�ƐM�`�͂����������ς�ʁB���͂��x�Ɛ��ɏo��]�݂͂Ȃ��A���U���̕������ƂɌ��߁A�邩�ɌF��ɗ��������ł������B
�@����ǁA�����g�����p�����������Ƃő��q�B�ⓛ��Ƃɍ߂��y�ڂ��悤�Ȃ炱�̏�ŕ����d�낤�B�悵�ȂɌv���ĉ�����B�v
�@�ƌ����]���������B
�@��������Ĉꓯ��
�u���ꂼ�g�m�͌Ȃ�m��҂ׂ̈Ɏ����h�̌��ʂ肶��B���ʊ��ҁi�G�g�j��������遂��ĉ��Ɖ]�����Ƃ����Ŏ��Ȃ��Ă͑�a���m�̒j��������v
�@�ƍ���̑�����c�̖���
�u���q�ɎQ�����ӂ͗ǍO����g�ɕ����A����J���n���đm�ƂȂ荂��A�F��ɓ���B��ˉƂ͒��j�E�o�O������ƂȂ�A�㌩���͍��܂Œʂ���\�Y���߁A���c�͍߂��ނ�ɋy�ʂ悤�������i��s���v
�@�Ɗm�āA�����邱�Ƃɂ����炵���B
�@�V���\�N�i��ܔ���j�Z���\�l���̖锼�A�ǍO�͎��j�E���G�Ƌ͂��ȘY�}�Ƌ���ꠓ����邻���ɔ����o�Ďp���������B
�i�X�j�킢�̌�
�@���\�ܓ����ɓ��䏇�c���x��y���Ȃ�����̏G�g�{�w�Ɏp��������B�����ʂō��ɂ����̗������C�ȏG�g�ɁA���c�͓������ɏo�������̂͑�R�ł��鎖��ى������B���̏�ŗL���ȁu�T�䓛�v�̈�˒��q�������o���A�ǍO�̖��q�ɎQ��������𖾂炩�ɂ��Ęl�т��B�G�g��
�u������Ȏ����I�v
�@�Ƒ劅���������ŁA��͉����Nj������@�������Ɖ]���B�g��������肷�鎖�Ɛl���炵�̖��l�h�Ɖ]��ꂽ�G�g�����ɁA���c��ǍO��ӂߗ��Ă鎖�����A���̈�˒��q�𗘋x�i*1�j�Ɍ����悤�ƍl�����̂��낤�B�����ė��x�𒃓��i*2�j�Ƃ��Ď��̓V���l������R�����A�₪�Č����N����ēc��Ƃ̓V�����ڂ̑���ɑ�a�O�𖡕��ɂ���̂������B�c�ƁA�f�����Z�Ղ��͂������ɈႢ�Ȃ��B
�@�����Č���A�g�c�����i*3�j�����G����喇�̋�q�������������炩�ƂȂ��Ă�
�u�r����������ʎ��v
�@�Ǝ��������̂́A���̋���ԋp�����A�s��ɂ��Ă���̂��������R����ł��낤�B
�@�Ñ�V�c�̐e���̐��͂Ƃ������A���v�̗��⌚���̒����Ȃǂ̒ɂ��o������V�c�͎��猠�͂����炸�A���̌��͎҂̈ӂ��}������u�����ƓV�c���쎝�v�����߂�̂����̓`������ł������B
�@�]���āu�s����Α��v�̌��ʂ���G�������ɂ܂݂ꂽ�̂����R�Ɖ]���悤�B
�i*1�j�痘�x�i����̂肫�イ�j�B1522�`1591�B���l�B���������̂��Ȃ��Ƃ���܂Ŗ��ʂ��Ȃ��āA�ْ��������o���Ƃ����u��ђ��i�����̒��j�v�̊����҂Ƃ��Ēm����B���\�̂Ƃ��A���x�́A�ˑR�G�g�ɋ��s���ڊy���~���Őؕ��𖽂�����B����A���x�̎�͈��ߋ��Ş���B���߂̗��R�͒肩�ł͂Ȃ��B�u�l�����\�@�͈͊��@�ᔇ�����@�c�ŋ��E�@��i�Ђ������j��䓾��̈ꑾ���@���������V�ɝe�i�Ȃ����j�v�i�����̋�j
�i*2�j���ǂ��B�u�����v�u�����v�Ƃ������B�M�l�Ɏd���Ē����������ǂ������̎t���B���y���R����ɐ�@�Ձi���x�j�E�Óc�@�y�炪�M���E�G�g�̒����߁A�]�ˎ���ɂ͊e�˂ɂ��������Ƃ����E�����ł����B
�i*3�j�悵�� ���˂݁B1535�`1610�B���s�̋g�c�_�А_��̐_���ƁB�w�������L�x�̒��ҁB
�i�P�O�j���I���@�`�F�����Ղ�K�˂ĂP�`
�@�����L���J�����B
�g���a�l�\���N�i��㎵��j�\���A����R���m�@�ɗї�����M���A�G�g�A�ƍN��e�҂̕��𑁋łɈꏄ���ĎO��@�Z�E����
�u�s�v�c�Ɍ��G���̕悾���́w�\�͋t�b�ɔx�Ƃ悭����鎖������v
�@�Ƃ̔�b�����B�h
�@�R��V���R�̌Ð������܂悤���Ⴋ������O�\�]�N�̍Ό����ւ��������N�i��㔪��j�̍��炭���B������Ƃɂ���ʗ��j�̉����w�сA���߂Č��G�I���̒n��K�˂č��������悤�Ǝv�������A����d�Ԃɗh���ĕ����Ɍ������B
�@���̓����͍g���̏��Ƃœ�����������������w��̘Z�n���ō~��āA���I���s�̃o�X�ɏ�����B���I���̃o�X�₩�獶��̎R���ɓ���ƁA��ϔ��N�i���Z�Z�j�I�Ó����j�R���番�삵�����I�����̑����甪���_�Ёi*1�j�����܂��Ă���B�y���̌��G�����̎БO�ɐ_�����F�����̂͂��ꂩ�玵�S�]�N��ɂȂ�B
�@����������E�ɐ܂�ĎR�H��H��Ɩ{�o���Ɖ]����������A���̗���̒|�M�����Ɂu���q�M�i*2�j�v�ƌĂ����G�I���̒n�Œւ̌Öɂ͖����̉Ԃ��炫�����Ă����B
�@���������o�Ă���Ö鎵���̓����s�Ɉ�s�͔����Ď��R�ƌx���S���݂��Ȃ�A�Ђ����犩�C���ւ̓����}������B�^�t����ȕГc�ɂ��M�̒��ɂ܂ŋ��n���҂��Ă��悤�Ƃ͖��ɂ��l���Ȃ������낤�B
�@�ւƒ|�тɈ͂܂ꂽ�u���q�M�v�̔�ɂ͗��l���������炵�������ƕ��Ԃ��͂�c��A�y�X�Ə����ɗ������Ԃ��ւ̉Ԃ����̂����G�̌��ɂ܂݂ꂽ����v�킹��B
�@�u�̊`���ŕS�㒹���������܂��������B���̌����ɑ��O��@�̉������ނ��Č�����B�u�S���y���͉��䂫���́v�Ɖ]�������G���y���̒|���ōŌ���Ƃ����̂�����łȂ�Ȃ��B�V����������������ɋ������B���̖������F��A�Î�Ȓ|�т̒��ňꕞ����B��O�̌F���������b�N�ɓ���Ă��߂Ă��̋L�O�Ƃ��A�ʂ���������B
�i*1�j���s�s�����揬�I���{�R���B�Ր_�́A���_�V�c�E�����V�c�E�_���c�@�B���a�����̑c�ł��鐴�a�V�c�̌��A���7�N(865�N)�ɕ����h�H(������)�̎q���ł���I�Ó��Ɋ֓��̎��𖽂����B�����ɍۂ��j�R�����{���Ր_���������A���I�������{�Ƃ��ē��n�Ɍ����B���I���̎Y�y�_(���Ԃ��Ȃ���)�Ƃ��Č��݂Ɏ���B
�i*2�j���s�s�����揬�I�����㒬�B1990�N�ɋ��s�������C�I���Y�N���u�����Ă���ɂ́A���G���P�����̂͐M���̋ߐb���I���ق̔ѓc�ꑰ�ƋL����Ă���B�X�����R�ȕ��ʂ�20�����x�����ƁA���q���G�̓��˂̔肪���B
�i�P�P�j���I���@�`�F�����Ղ�K�˂ĂQ�`
�@�F���w�ɒ������B���̒����ɂ��钃�̖��������ݏグ��̂ŗL���ȎO�m�Ԃ̗����ɗ��ƁA�����X�̐�ʂ��琁���グ��앗���g�ɂ��݂�B
�@���֖̊�ŗL���Ȃ��̒n�́A���v�̗��ȗ��̌����ŗǂ��m���Ă�����
�u�܂�����Ƃ̑c�悪���Ƃ��Ďl�N�Ԃ��x�z���Ă��悤�Ƃ͖��ɂ��C�Â��Ȃ������i�v
�@�Ǝv���Ȃ���A���ォ��F�������@�߂��B���O�ʗ��������n������̎ł̔ޕ��ɘA�Ȃ�R�X�B�_�X�Ɣ����R���������R���Ɍ��Ƃ�Ȃ���F������n��B���݂̒�h�����ɉ����čs���ƒ��F�Ɋ��̌Q�ꂪ�}�������a���������Ă����B
�@�̂͐쒆�̏����Ŕ_���̋߂��̒��������̏�Ղ��Ɖ]�����A�Ί_��c���Ă��Ȃ��B���R�`�����M���œ|�ׂ̈Ɏl��߂��R���ď邵���������瑊���ȏ�s�������낤���A��ɏG�g�������z��ɍۂ���ĉ^�ы������炵���B
�@�uꠓ���Ձv�Ƃ����ɂ͑����Ō�̏��R�������`���̂��Ƃ����L����ĂȂ��B�y�n�Ɏc��G�s�\�[�h�ł��Ȃ��낤���Ƌ߂��Â߂��������@��K�˂����A��˗ǍO����傾�����̂��m���Ă��Ȃ��B����͔s�҂̏킩���m��ʁB
�@���c���ǍO�ɉ����ė����n��G�g�̕��w��˂��A�Ⴆ�s��Ă������͎c��Ȃ������낤�ɂƎv���B
�@�܂��ď��c����N��Ɏᎀ���āg���a�����c�h�̉������c���A�{�q�莟�͗̒n������Ĉɉ�Ɉڂ���A�₪�ĉƍN��㩂ɂ������ĕ��q���ɐؕ����A����Ƃ͈���f��ł���B�߉^��H��̂�\������Βf�s�����낤�Ɂc�B�u�_�Ȃ�ʐg�̒m��R���Ȃ����v�ƍl���Ȃ���F�����ɖ߂����B�܂���t�̗[���������̍Ō�̌������R���ɓ��������A���悮�앗���g�����B
�@�t�g�q�H�i*1�j��
�u�t�̗[��Ɏd�������̒��������Ď�ҒB�Ɛ앗�̂��悮�y��̓�������̂����̖]�݂ł��B���ɏ����ۂ��Șb�Ő\��Ȃ��v
�@�Ɠ��������ƁA���̌��i�ȍE�q��
�u���Ȃ�A���Ȃ�A���������v���B�v
�@�Ɠ��ӂ����G�s�\�[�h���v���o�����B
�u�������O�\�N�́A�R��̌Ð�������Đ��n��A���{�̑K���ł����ς肵�Ĉ�t������B���̍g���̒���K�˂āA���̒��̗������ڂ��A�n���M�ɂ���ċA��̂������Ȃ����v
�@�Ɗҗ�̋߂��V�̐g���Y��Đ����悭�F���w�Ɍ������B
�i*1�j����B�O543�`�O481�B�����A�t�H����̐l�B�E��\�N�̈�l�B�D(��)�̐l�B���͒��A���͗R�B���E�ɂ�����A�E�q�ɂ悭�d�������A�q�̓����ŎE���ꂽ�B�G�H�B